「コレステロール神話」 (6) 動脈硬化 (2)
(
某日。
承前。
Jonny Bowden & Stephen T. Sinatra, The Great Cholesterol Myth, Revised and Expanded (Fair Winds Press, 2020) を読んでいる。
はっぴいえんどに続いて昔の音楽をかける。
はちみつぱい「センチメンタル通り」を聴く。
前回のエントリーで記したように、動脈硬化 atherosclerosis 過程が始まるのは、LDLが、ダメージを受け破れた動脈壁に入りそこに留まって酸化炎症反応過程を開始するとき。
炎症が生じると免疫システムが異常を感知しマクロファージを送り込む。マクロファージは「不法占拠」LDLを飲み込み続けやがて死ぬ。死んだマクロファージは foam cell 泡沫細胞と呼ばれプラークを形成していく。まだ内壁の一番奥の層 tunica intima 内膜に留まっている。
次に、血管壁を構成する平滑筋細胞が直ちに異常を感知し、内膜に移動してプラークの上に瘡蓋のようなもの (fibrous cap 繊維性皮膜) を形成する。平滑筋細胞は、泡沫細胞の多さに困惑し、ここに骨を形成しようと考え、プラークと瘡蓋のあるところにカルシウムを沈殿させる。異物が大きくなる。
プラークと瘡蓋は内膜から血管に突き出してくる。反応は2つ。1つは血管の直径が縮み進入に対応する。血液が流れにくくなる。もう1つは、カルシウム沈殿の影響もあって、血管壁が柔軟性を失いこわばってくる。動脈硬化。プラークが破裂しそれを構成していた脂肪が血液内に入ると、血液は異物混入を感知して、その異物が血流内でひろがらないように血栓を作る。血栓は防御メカニズムなのである。しかしこの血栓のせいで硬化した血管が詰まりあるいは血液が十分に流れず十分な酸素が各所に行き渡らないことがありうる。心臓の場合心臓発作を引き起こす (also p. 74)。
LDL粒子が問題なのではない。LDLが本来入り込むべきではない場所 (傷ついた内皮細胞の層) に入り留まり、酸化・炎症物質による攻撃を引き起こすこと、それが慢性的炎症に至ること、が問題なのである。とすればそもそも内皮細胞の層 endothelium が刺激物に晒されたり破れたりするのを防げば良い。
方策は3つ。まず、心臓血管の損傷が常に内皮膜endotheliumの損傷から始まることは述べた。こうした損傷を引き起こす刺激物・有害物質への曝露を減らすこと。次に、LDLを、本来あるべき場所ではないところから遠ざけること。最後に、LDLの酸化・炎症反応を防ぐ・減らすこと。
酸化。LDLは酸化するまでは体内では問題ではない。酸化していないLDLは無害。その酸化、そしてそれが引き起こす炎症が動脈硬化の開始因。
“LDT particles are not the problem—LDL particles winding up in the wrong place and then getting attacked by oxidative and inflammatory compounds is the problem” (p. 63).
“LDL is not the problem in the body until it becomes oxidized. … It’s oxidization—and its partner in crime, inflammation—that actually initiates the process that culminates in atherosclerosis” (p. 71; emphasis in original).
LDL酸化原因は、タバコ煙、水銀といった金属、殺虫剤、放射線、環境・空気中・食品中のさまざまな有毒物質、など。
“It’s not just cigarette smoke that can oxidize LDL. Heavy metals like mercury can do it, as insecticides, radiation, and all manner of toxins in the environment, the air, and the food supply” (p. 70).
これらへの曝露を減らす必要がある。
上述の箇所ではLDLが問題になるのは酸化したとき、とあるが糖化glycationされた場合にも問題となるようだ。
最近発見されたLDLの下位類型であるMGmin-low-density-lipoprotein は、動脈壁に固着し炎症を惹起する極悪 “ultra-bad” のLDLコレステロール。2型糖尿病や高齢者に多く見られる。正常なLDLに比して粘着性が高く心臓血管壁に遥かに付着しやすい。付着すると酸化・炎症を招く。
この「極悪LDL」は実のところ糖化glycation過程により産み出される。糖化は血液中に浮遊する糖質が多すぎる場合に起こるプロセス。過度な糖質は代謝過程を台無しにし、それがあるべきではないところ、例えばLDLに入り込む。LDLはglycation過程を通じて「極悪」LDLになる。(also pp. 91-92)
“[a] subtype of LDL … called the MGmin-low-density-lipoprotein, is more common in people with type 2 diabetes and in the elderly. It is much “stickier” than normal LDL, which makes it much more likely to attach to the walls of the arteries.”
“[T]his “ultra-bad” boy is actually created by a process called glycation. Glycation happens when there’s too much sugar hanging around in the bloodstream” (pp. 69-70; emphasis in original).
糖質については後続のエントリーで述べる。
酸化したLDLが心臓血管壁の下 (損傷したendotheliumの隙間から)に入り込み炎症過程を引き起こすことが、さらなる炎症と損傷を引き起こす。LDLには損傷・酸化を最も被りやすいタイプがある。それらは内皮膜の損傷部分から入り込めるほどに小さい。また粒子が小さければ小さいほど炎症的である。酸化や高血糖による損傷によりこのLDLは「極悪」になり、免疫システムが危険だと感知して炎症反応が起こる。
食事とコレステロール。人口の0.4%程度を占めるとされる家族性高コレステロール血症 (familial hypercholesterolemia) 以外は、食事由来のコレステロールはその血中濃度に影響を与えないことが、コレステロール組成の話を絡めながら述べられている。
“For 99.6 percent of the population, eating cholesterol makes absolutely no difference to your blood test cholesterol” (p. 65).
“The exception is for the 0.4 percent of the population with a genetic condition known as familial hypercholesterolemia” (p. 66).
続く。
)
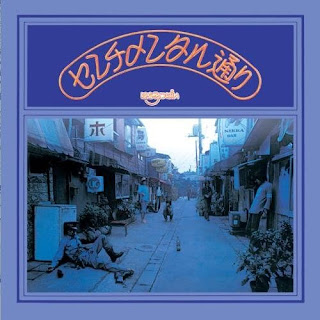
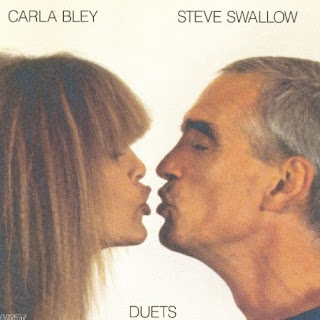


コメント
コメントを投稿