日本橋でグループ展を観て勝手に考えてしまう
(
某日。
自宅にて自炊第2食目を摂る予定で午前中に外出する。好天。
交通機関を乗り継いで地下鉄日本橋三越駅で下車する。いつものように地下食品街から三越本館に入る。ゆっくり一回りして視覚と嗅覚を刺激してから6階に昇りコンテンポラリーギャラリーに行く。
開催中の東京藝術大学大学院美術研究科油画第6研究室による企画展『ピテカントロプス Project by The 6th Laboratory Oil-Painting Department of Tokyo University of the Arts』を観る。
敬称略。
薄久保香
東京藝大の研究室ということでこのような場や類した場で発表できる可能性が高まる、という特権があるのかもしれない。この特権の利得込みで、1番難しく権威があるとされている東京藝大を目指す、に入る、ということもあるのかもしれない。そのためにそうでなければしなかったかもしれない苦労や努力をするということがあるのかもしれない。最初からどの制度を経ても発表機会は平等だというのなら、異なる場所で異なる学び方をする人が増えるのかもしれない。どの制度を経由するかによって事実上その後の発表機会や発表のしやすさに差があるということがある程度確認されているのなら、この差を考慮に入れた上で制度を選択するというのはこの文脈では合理的な判断だという言い方もあるだろう。外部から見ればこうした差は不公平なのかもしれない。ただ、これからある制度に入って行こうとする若い人に、すでに存在するこの差の是正をするよう求めるのは酷な話のような気がする。この差の存在が制度選択の理由の一つだった場合、学んだ後でいざ発表しようとするときに「この差はなくしましょう」といわれると、この制度で学んだ人の中には「話が違うじゃないか」と思う人がいてもおかしくないと自分には思える。
鑑賞者が作家の経歴といった外部情報を括弧に入れて作品だけを観て自分の価値基準・感受性で味わうようになれば、このような学歴に紐づいた特権がなくなるという考えもあるだろう。これはしかし難しそうだ。このように鑑賞したいし鑑賞できる人は少数だろう。というのも、進化論的に人間は社会的動物で、一般的な他人からの自分の評判・評価 (reputation) をとても気にして重視するように脳ができているからだ。例えば Kevin Simler and Robin Hanson, The Elephant in the Brain: Hidden Motives in Everyday Life (Oxford UP, 2017)
他人から見た自分の鑑賞センス・美的価値判断の評価がとても気になる。それを満たしていればその作品は一般的に評価されているとみなされる可能性が高い、そのような指標や基準があれば楽だろう。その指標や基準を満たした作品に反応していれば他人からの自分の評判・評価へのおそれが小さくなるからだ。美術館に所蔵されている「評価」の定まった物故作家の作品なら問題なく鑑賞できるだろう。現存の、評価の定まっていない作家の場合、そうした指標の一つは学歴を含む経歴だろう。東京藝大を出ている。受賞している。美術館に所蔵されている作品もある。「だから」そうした作家の制作する作品は良いのだろう。著名人、メディア、批評家などによる肯定的な評価が暗黙の基準になる場合もあるだろう。そうした基準を知っていればさらに安心するだろう。彼らがそう評価しているの「だから」良い作品なのだろう。作家の学歴や収蔵歴などの情報を括弧に入れ作品だけを観て自分の感受性と価値基準で味わうには、ある程度脳の初期設定に逆らって観る必要があるのだろう。その分、脳に負荷がかかるだろう。これを鑑賞者に要求するのは酷な話だろう。もし要求するのであれば、要求の背後には、作品だけを観て自分の感受性と価値基準で味わう「べき」、味わった方が「よい」という規範が隠れているだろう。なぜ「べき」なのか、なぜ「よい」のか、なぜ「よい」ことをしなければならないのか、それほど明らかではない。そのように観たいし観ることができる人はそのように観る、そうでない人は異なる基準で観る、ではダメなのだろうか。
茨木のり子の詩句「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」を思い出す。科学を持ち出して詩を字義通りに受け取るのは野暮なのだろうけれども、「自分の感受性」「自分で守る」ということがよくわからないのだった。具体的には、進化論心理学や脳科学などの知見を考慮すると、自分を内観しても、どこまでが「自分」の感受性なのか、外部から勝手にインストールされた感受性の形式を「自分」のものだと半ば必然的に錯覚したものが「自分の感受性」なのではないか、それなら「自分」とは何か、などなど。言語を使う以上「自分」「私」などとは言うけれども、感覚・感受性というものは自分のうちにどういうわけか生じてしまうもの、という実感がある。自分「の」感覚・感受性と言っても、「の」は自分が生み出し所有するという意味ではなく、仮に自分と呼ばれるもの「の中で」「のうちに」という場合の「の」という感じだ。そしてどこまでこのような「自分の感受性」を「自分で守れ」るのか (自由意志は幻想ではないのか)、わからないのだった。上掲の書籍に加えてMatthew D. Lieberman, Social: Why Our Brains Are Wired to Connect (Crown, 2013) やDavid M. Eagleman, Incognito: The Secret Lives of the Brain (Canongate Books, 2011) など。
誰に頼まれたわけでもなく、上述のような特権を伴う制度を変えるために行動するわけでもないのに、勝手にいろいろ考えてしまう。脳のエネルギーの無駄遣いだろうか。
ギャラリーを出る。同フロアーで開催されている他の展示もざっと観る。
久しぶりにクラムボン、Musical
三越地下街を抜け三越前駅から一駅乗車して日本橋駅で下車する。
高島屋本館に入る。本館2階アートアベニューで開催されている卯月俊光展 「―KiLaLa―」を観る。お店の間を歩きながら観るようになっている。
美術フロアーである6階に昇り、開催されている複数展示をざっと観る。写真は撮影しなかった。ハシビロコウの木彫があった。
日本橋高島屋を出る。
6:00 起床。NY市場終値をチェック。
グラス一杯の水を飲んで柱サボテンとボトルツリーをヴェランダに出す。
シャワー。
大きめのカップに珈琲を淹れる。オーガニック豆 20g、260ml。飲みながら読書。
スロージョギング。腕立て伏せ15回x 10セット。
9:00-9:30 第一食。自炊。マグネシウム (にがり顆粒 2g)、ビタミンB (Dear-Natura Mix)、ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g)、ビタミンD3 (Health Thru Nutrition 10,000Iu)、亜鉛 (Dear-Natura, 14mg)、ルテイン、ゼアキサンチン、コリンサプリ、タウリンサプリ (1000mg)、ナイアシンアミド (500mg)、イヌリン粉末 6g、グリシン粉末 3gを摂取。
ストレッチ。ホットココア (オーガニック、非アルカリ処理)。
雑用。外出。
)



















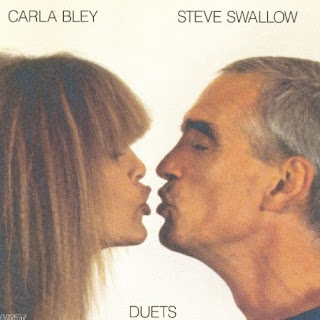


コメント
コメントを投稿