矢野静明作品をお迎えする (1)
(
某日。
前回エントリー「矢野静明氏のアトリエに伺う」の続き。
アトリエに伺った際、絵画作品を2点お迎えした。
1点目の画像
サイズ: 140x180(mm)
油彩・インク・キャンバス
小品 (サイズ0号) とは思えない密度のある作品。以前からなぜかひどく気になっていた作品で、ここ2年ほど作品画像をiPhoneに保存して時折見ていたのだった。
今回のアトリエ訪問に際して、この作品を拝見したいということも、お迎え検討の意志があるということも、お伝えしていなかった。
ところがアトリエ内の作品をいろいろと見ると、なぜかこの作品がなぜか置いてあった。「矢野静明氏のアトリエに伺う」最初の画像、右下に黄色い小品が1番上に置かれてその下にいくつか作品が平積みになっている。その黄色い小品の2つ下にあるのが上掲画像作品。
作家本人が2階にあるリビングの壁に長い間かけていた作品で、たまたまアトリエに持ってきており近いうちに2階の壁に戻すつもりだったとのこと。自分も平積みの作品を抜かりなくチェックしてこの作品を見つけたのだった。拝見してやはり大変良い作品だと思う。
他にも自分側の条件が重なり、これはそういうタイミングだと思い、お迎えすることに決めた。そのために2階から1階のアトリエに降りてきたかのようですね、とは作家の言。作家にそのように言われると嬉しく思う。初めて所蔵する0号作品になった。
作品の物理的サイズ、作家が描く線・色彩・形態の作る絵画空間のスケール、観ることで鑑賞者に生じる感覚のスケール。短いけれども極めて充実した『セザンヌは何を描いたのか』(白水社、1988) の中で著者の吉田秀和が述べていた絵画の3つの層 (特にpp. 31-)。作家が意識するしないに関わらず、どの絵画作品も、分離しつつ共存するこれら3層を程度の差はあれ持っているのだろう。
吉田秀和はセザンヌの絵画分析でこれらの3層を論じていた。セザンヌは3層の分離・共存・統合を明晰に意識して絵画制作に取り組んでいた、と。日本で容易に数多くの実物を観ることのできる作家としては、熊谷守一の小さいサイズの絵画作品などにこのようなサイズとスケールの感じがある。例えば豊島区立熊谷守一美術館において。
所蔵している矢野さんの作品はどれも、自分にとって作品の物理的サイズに対応する大きさを超えたこれら2つのスケールを感じさせる。上記画像の作品からも、0号でありながらそれを遥かに超えたスケールを感じる。あるいは自分にとってこうしたことが感じられる作品を選択して所蔵しているということかもしれない。
こういうことがあるからだろうか、矢野さんの作品は自分にとって観る時間と熟視を要するものばかりである。観て感じる瞬間的な強度とは別に、遅く徐々に深まっていく強度も感じるのだった。
なお、Megiddo は旧約聖書に何度も登場するイスラエルにある丘の名前。「聖書ゆかりの遺丘群」として世界遺産に登録されているようだ。
ヘブライ語の「メギドの丘」のギリシャ語表記が「ハルマゲドン」のようだ。
The Police, Synchronicity を聴く。



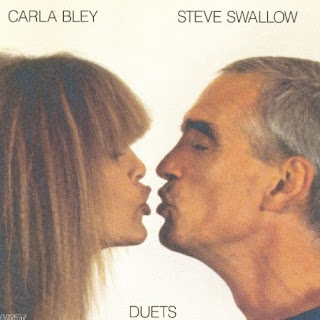


コメント
コメントを投稿