昔読んだ色川武大「うらおもて人生録」のこと
(
某日。
エントリー「交通の乗り継ぎが良すぎる」で言及した書籍について。
「運は通算するとプラスマイナスで相殺され結局ゼロ」
「適当な負け星を引き込む、選定する」
「9勝6敗」を目指す
「持続」を軸
運の配分は一個人の人生の内部の話だろうか。そうだとして、自分の人生の中で、幼年、思春、若年、壮年、老年、それぞれの時期の運の良し悪し・重要度を「通算」「相殺」できるような共通の単位があるのだろうか。人生を振り返るその時々の自分の状況に合わせて、自分の都合の良いように運の良し悪し・重要度を含め人生を意味付けているということはあるだろうか。
ある不運なことが、後の幸運なことにたまたま繋がった場合、後者が生じた後で、前者はもともと後者の一部をなすだったものとして、ある連関の中に組み込まれ位置づけられ意味付けされ統合されるかもしれない。ある不運なことと後の不運なこと、ある幸運なことと後の不運なこと、ある幸運なことと後の幸運なこと、といった組み合わせもあるだろう。
2つの出来事間だけではなく多くの出来事間の様々な連関があり、連関をどう区切るかによっても意味付けが異なるのだろう。
あるいはある不運なことを他の出来事との連関の中に位置付けて意味を与えることができない場合、不運さがより強く感じられるかもしれない。幸運なことの場合は幸運さが一層輝いて感じられるかもしれない。あるいは連関や意味を捏造するかもしれない。
こうしたことは、記憶の改変やいわゆる認知バイアスが様々な形で働くことで生み出されているのだろう。こうしたことは、自分の中でも気付かないうちに生じているのだろう。
運は通算で相殺されゼロだとしてみる。ある環境下で生きる人の運が通算で相殺ゼロになる場合と、別の環境下で生きる人のそれの場合とは、相殺ゼロだから同じこと、と考えられる、考えるべき、だろうか。
例えば現にひどく恵まれている人とそれほど恵まれていない人がいるように思える。ある程度の年齢になるまで恵まれていた人は、これから「負け星」を何らかの形で引き受け、人生の終わりには運の通算は結局ゼロ。ある程度の年齢にまで恵まれなかった人は、これから「勝ち星」を何らかの形で重ね、人生の終わりには運の通算は結局ゼロ。そういうことだろうか。
あるいは今までそれぞれ9勝6敗を目指したとして、一方は9つの勝ち星の規模を大きく、6つの負け星の規模を適切に小さくして、営みを持続拡大した。他方は9つの勝ち星の規模は小さく、6つの負け星の規模は致命的なまでに大きくして、日々の暮らしが辛いものになった。そういうことだろうか。
何を「勝」何を「負」と見なすか、勝ち負けの大小をいかに評価するか、満足度、幸福度、はそれぞれにとって異なる。傍目にはあまり恵まれていないように見えるけれども本人は満足している。それぞれの人生の内部で、それぞれの基準で、運の通算はゼロ。そういうこともあるのかもしれない。
あるいは例えば二人の人生が運の配分単位という考えはあるだろうか。恵まれた人生とそれほど恵まれないと傍目には見える人生を合わせて「運は通算するとプラスマイナスで相殺され結局ゼロ」。そう言えるだろうか。言えたとして、それほど恵まれていない日々を送っていると感じる人は納得するだろうか。あるいは、兄弟姉妹間、ある家族と別の家族、ある世代と別の世代、ある国と別の国。
検証できる事ではないのだろう。他人との比較が可能であるための共通の物差しがあるかどうかもわからない。比較したいと思うことにも実際に比較をしてみることにも何かしら傲慢なところがあるのかもしれない。比較をしなければ気付かなかったであろう新たな視点や認識を得るとしても。
統計的に極めて大きな枠組みで見れば運の良し悪しというものには意味がない、という考えもあるだろう。当籤確率1,000万分の1の宝くじは、1,000万回買えば大体1回当籤するだろう。1,000万回分見渡すことができて、且つ、当籤する時期を問わないのであれば、ただ確率が1,000万分の1というだけで運の良し悪しはないかもしれない。一人の人生という枠組みでは、しかし、買うことのできる回数は限られており、且つ、当籤のタイミングも重要だろう。こうした小さな枠組みでは運の良し悪しがあるようにも思える。
結論はないけれどもこの書籍に触れたついでに思ったことを、Friedrich Gulda, J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier を聴きながら書く。
バッハを聴くと頭がスッキリするというかシャッフルされる感覚がある。弾いたらもっとそのように感じるのだろうか。
)


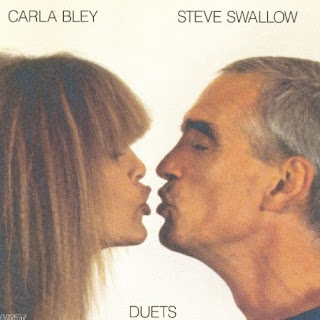


コメント
コメントを投稿