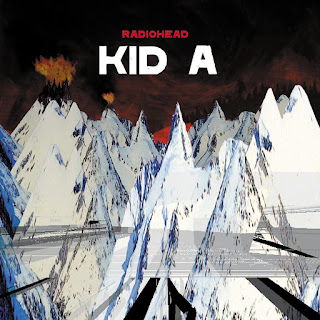象徴主義絵画の書籍を読了し俵屋宗達の書籍を読み進め料理を作る

( 某日。 終日在宅。 SJQ (Samurai Jazz Quintet), Animacy などを聴く。2009年の作品。11年ぶりの新作 Torus が2020年に出ていたようだ。知らなかった。音楽のチェックを怠って久しい。 Michael Gibson, Symbolism (Taschen, 2006) を読了する。 ドイツ語圏諸国とスカンジナビア; スラヴ文化圏; 地中海地域 (イタリアとスペイン); 象徴主義以後、の3章、110ページほど。 「ドイツ語圏諸国とスカンジナビア」の章で掲載されている画家のうち、知っているのはフェルディナント・ホドラー、クリムト、ムンクだろうか。載っていて知らない画家。Otto Greiner, Arnold Böcklin; Ludwig von Hofmann; Julius Klinger; Max Klinger; Franz von Stuck; Alfred Kubin; Carlos Shwabe; Hugo Simberg; Akseli Gallen-Kallela; Magnus Enckell; Halfdan Egedius; Ernest Josehpson; Jens Ferdinand Willumsen. 「スラヴ文化圏」の章で知っているのはミュシャ (ムハ)、カンディンスキー、マレーヴィチのみ。掲載されていて知らない画家。Bruno Schulz; Frantisek Kupka; Jacek Malczewski; Jan Preisler; Karel Masek; Wladyslav Podkowinski; Witold Pruszkowsi; Józef Mehoffer; Jan Matejko; Stanisław Wyspiański; Witold Wojtkiewicz; Stanislaw Ignacy Witiewicz; Mikhail Alexandrovich Vrubel; Léon Bakst; Alexandre Nicolas Benois; Victor Samirailo; Ilya Repin; Vassili Denissov; Kosma Petrov-Vodk...