「日記人格」と報酬系 (ブログ人格、SNS人格)
(
某日。
5:30 起床。NY市場終値をチェック。
グラス一杯の水を飲んで柱サボテンとボトルツリーをヴェランダに出す。
シャワー。
珈琲を淹れ読書。
中井久夫氏を読み返していたら次のような指摘が目に留まる。
“日記も、読まれることを予想して書かれることがしばしばある。永井荷風の『断腸亭日乗』やジッドの『日記』は明らかにそうであろう。精神医学史家エランベルジェは、日記を熱心に書きつづける人には独立した「日記人格」が生まれてくると言っている。日記をつける人も読む人も、このことは念頭に置くほうがよいだろう。”
中井久夫「伝記の読み方、愉しみ方」『日時計の影』(みすず書房、2008) 所収 pp. 248-260; ここでは p. 249。
Henri F. Ellenberger の発言の原典は記されていない。
エランベルジェの著作で所有しているのは The Discovery of The Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry (Basic Books, 1981) のみ。この著作中に上記発言があるのか、976ページもの長さにたじろいでチェックせず。
脳は、食べ物やお金からよりも他人に対する自分語りから大きな喜びを得るという研究報告がある。
Diana Tamir and Jason Mitchell, “Disclosing information about the self is intrinsically rewarding,” in Proceedings of the National Academy of Sciences, 109, 21 (2012), 8038-8043
“intrinsically rewarding” というのは脳の報酬系 reward system が本来そのような機能を備えている (intrinsic) ということだろう。人間の意識・意志に関わらず、程度の差はあれ脳はそのように機能する、機能してしまう、ということだろう。
日記を誰にも知られることなく自分のノートに書くのではなく、ブログで書き公開する。そのブログには、読まれることを予想した他人に対する自分語り、という側面が必ずあるだろう。その側面には他人から自分がどのように見られるか・見られたいかということが含まれているだろう。そうして報酬系が刺激されているのだろう。
直接的な自分語りがなくても、例えば画像とキャプションのみの、加工なしキャプションなし画像のみのインスタグラムでも、あるいは事実内容の記述だけでも、公開するなら同じことが言えるだろう。
このタイミングで、このデータを選び、この仕方でアップロードする、アップロードできる自分。表現された自分 (内容)、に加えて、表現する自分 (形式、振る舞い)。
あるいは、言葉での自分語りも画像アップロードもなく、他人と同席するだけの状況でも同じことが言える場合があるだろう。そのような隠微な “Disclosing information about the self” もあるのだろう。それは “intrinsically rewarding” なのだろう。
例えばもっぱらバーでしか会わないお客同士が賑やかに自分語りを含めた会話をしているバーで、会話に加わらず静かに呑んでいる場合。言葉での自分語りはしていない。そうした自分語りには興味がないのかもしれない。けれども、そのような状況でそのように振る舞うことそのものが、他人に対する一つの自己表現の形式・呈示になってしまうだろう (物静か、クール、取り澄ましている、とっつきにくい、等々)。他人が集まることが前提の場所に行ったのに、自分が他人からどう見えるかを全く気にしないということは、人の脳のプログラムとして通常はあり得ないのだろう。
進化論的に人間の脳は根本的に社会的なものとして作られているようだ。社会的繋がりを構築するために予めプログラムされている。他人からの肯定的評価・評判を恥ずかしいまでに渇望しているため、自分が交流を望まないよそ者であっても、その人が自分のことを良く言うと、脳の報酬系部位が活性化するくらいだ。
あるいは痛み。人は肉体的痛みを感じる。否定的評価を含む様々な種類と程度の社会的排除を経験した時、心の痛みを感じる。肉体的痛みと心の痛みを感じる時、ともに同じ神経回路が活動しているようだ。どちらも生存への脅威だからである。心の痛み、とは比喩ではないらしい。
あるいは信念。自分の信念を考える時に活性化する脳の部位とその神経的基盤がある。主に他者の信念が自分の信念に影響を与えることを許す脳の複数部位とその基盤がある。前者と後者の一つは著しく重なっている。セルフコントロールと社会規範を守ること、ともに同じ脳の部分(right ventrolateral prefrontal cortex)が司っている。自己認識と他人からの影響を受けることには同じ部分(medial prefrontal cortex)が中心的役割を果たしている。
他人が自分と同じことを好む場合のみならず同じことを嫌う場合でも他人との繋がりを感じるように脳が活動する。 繋がりを感じれば報酬系が活性化する。
人間の言動を理解する基本枠組みは「意図 intention」である。先に挙げたバーの例で言うと、「皆が会話しているのに加わらない、そのような振る舞いをすることで何を意図しているのだろう?」(どのように見えたいのだろうか、など)。語れば語ったで「このように語ることで何を意図しているのだろう?」となってしまう。
こうしたことや類することは、例えばMatthew D. Lieberman, Social: Why Our Brains Are Wired to Connect (Crown, 2013) に既に詳述されている。人間が何とも滑稽なまでに、恥ずかしいまでに、悲しいまでに、社会的な動物であらざるを得ないか、記されている。
逸れた話を戻す。
「日記人格」と報酬系は関係していそうだ。
この 「(括弧付き日誌)」を書き始めて1ヶ月ちょっと。
「日記人格」が、報酬系が、自分にとって適切な仕方で機能するよう配慮すること。
肝に銘じる。
(この文章を含むこのエントリーでの「自己表現」にも上述の報酬系のことが当てはまる。このような認識を持っていること・持っている自分の、このような形式での呈示。)
(追記。このエントリー関連。『「日記人格」 ダン・アリエリー』『「日記人格」 ダニエル・カーネマン キャス・サンスティーン』)
*************
9:00-9:30 第一食。自炊。マグネシウム (にがり顆粒 2g)、ビタミンB (Dear-Natura Mix)、ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g)、ビタミンD3 (Health Thru Nutrition 10,000Iu)、ルテイン、ゼアキサンチン、イヌリン粉末 5g、グリシン粉末 3gを摂取。
ストレッチ。ホットココア。
15:30-16:00 第二食。自炊。亜鉛 (Nature Made 10mg)、ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g) を摂取。
読書。音楽。
Coconut oil pulling。NY市場寄り付きを見る。
腹式呼吸、就寝。
)
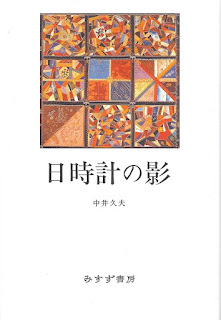

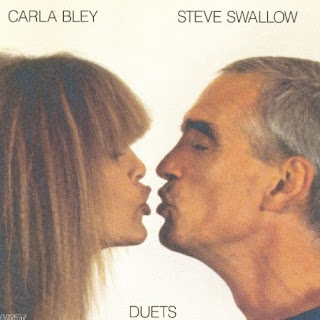


コメント
コメントを投稿