ひとりごとを言い3日ぶりに人と話しウィスキーを飲む
(
某日。
エントリー「佐藤誠高、ソー・ソウエン、荒木由香里、展を観る」の続き。
銀座駅から銀座線で渋谷駅に出る。
Susanna Mälkki and Los Angeles Philharmonic, Steve Reich: Runner / Music for Ensemble and Orchestra を聴いている。
エントリー『ひとりごとを言う能力「精神健康の基準について」』でも記したように、こういう状況だとたまにひとりごとを言っていることに気づく。
そのエントリーで記したこと。
********
中井久夫氏がひとりごとを言う能力について書いていたことを思い出す。
本棚から本を取り出し探してみると、精神の健康の基準の一つとして「独語する能力」を挙げていた。中井久夫「精神健康の基準について」、『「つながり」の精神病理』(ちくま学芸文庫)所収、pp. 237-248 (ここでは p. 247)。
「精神健康」とは「精神健康をあやうくするようなことに対する耐性」と定義され (p. 237)、17の耐性能力について述べられている。
「精神健康の基準について」は30年ほど前に違う著作所収版を読んで心を打たれた記憶がある。
引き続き本をチェックしてみる。
『精神科医がものを書くとき』(ちくま学芸文庫)所収「ストレスをこなすこと」では、独語についてのエピソードとして、国連からアフリカの奥地に独りで派遣され喋る相手が誰もいない状況で長期間過ごした人が、そういう状況下ではいろいろ独語していないと精神的にやっていられない、と中井氏に言っていたことを挙げている (p. 287)。
『世に棲む患者』(ちくま学芸文庫)所収「医療における人間関係-診療所治療のために」でも、ひとりごとについて同趣旨のことを中井氏に語った別の日本人のエピソードについて書かれている (pp. 225-6) 。
「壁に向かってひとりごとを言うより、人間に向かってひとりごとを言うほうが精神衛生にいいわけです。壁に向かってひとりごとをいっても、何も言わないよりましです」 (「ストレスをこなすこと」、p. 287)。
『「思春期を考えること」について』(ちくま文芸文庫)所収「教育と精神衛生」でも上述2エピソードに触れている。何度も言及していることからすると、中井氏はこれらのエピソードに強い印象を受けたようだ。事実、これらのエピソードは「私に壮絶な感銘を与えた」と記している (pp. 102-113; ここでは pp. 111-2)。「壮絶な感銘」とはあまり耳にしないフレーズである。よほどの感銘だったのだろう。
********
渋谷駅で下車してウィリアムモリス珈琲&ギャラリーに向かう。搬入でいつもより早い時間に閉店していた。行けばいつも店主さんと色々とお話をするので人と話す機会だと思ったのだが誰とも話さず。
それでも多様な展示をいくつも観て疲れておりコーヒーを飲みたい気分だったのでチェーン店に入る。飲みながら読書と音楽。
帰路、バーに立ち寄る。3日ぶりに同席したお客様と話す。3日間少ないひとりごと以外は発声していないせいか、声も喉もおかしい。絞り出すような掠れ気味の声。喉の筋肉を使ってなかったからだろうか。ニューロンも筋肉も、総じて "use it, or lose it"というのが当てはまるのだろう。
1時間ほどして喉も声もいつものものに戻る。面白い。
今週のお花
帰宅。
ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g程度) 、マグネシウム (にがり顆粒 2g) を摂取。
Coconut oil pulling、軽くストレッチと腹式呼吸、就寝。
)





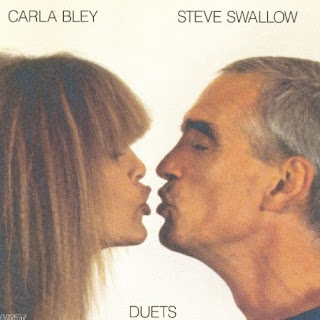


コメント
コメントを投稿