YUKI-SISで宮脇周作展を観て作品を購入する
(
某日。
エントリー「若林菜穂 個展を Katsuya Susuki ギャラリーで観る」の続き。
都立大学駅から中目黒駅まで東横線で移動して、中目黒駅で日比谷線に乗り換え、茅場町駅で下車する。
ギャラリー YUKI-SISにお邪魔して開催中の宮脇周作・河合真里 2人展「Still Life -静かないのち」を観る。
エントリー「YUKI-SIS で宮岡俊夫 個展を観る」で、「出来上がったばかりの次回展示DMの最終稿試し刷りを見せて頂く。参加作家についてのお話を聞く。とても良さそう。楽しみ。」と記していたのは今回の2人展のこと。
宮脇周作さん。日本テレビ専属法廷画家としてお仕事をされているそうだ。
今回の展示まで作家のことを知らなかった。作品も初見。これが素晴らしかった。展示の企画、ありがとうございます。
宮脇作品を1つ購入する。初めての静物画所蔵。
新しい生活のことがあり作品購入は控えていたのだけれども、この展示の直前に1作品なら購入することができる程度の懐事情になる案件を知る。作品を観る時期と懐事情の変化のタイミングが重なった。佳き出会い。
購入作品
242 x 333 (mm) (F4)
油彩、キャンバス
上述のDMに使用されている作品。どの展示作品も素晴らしい中、自分にとってはこの作品が突出して素晴らしく感じられた。売約済みでなくて本当によかった。
なぜとりわけこの作品に惹かれたのかはよくわからない。エントリー「特定の絵画作品に惹かれる理由についての学術論文を読む」で記したようなことはあるのだろう。自分の諸感覚と記憶の総体を揺さぶるような質の力を感じる作品だった。食べ物としてのりんごは嫌いだったことはないが大好きということも今まで一度もなかったのだけれども。
セザンヌのりんごは大好きだ。セザンヌは「りんごひとつでパリを驚かせてみせる」と語ったと言われている。Cézanne is reported to have said "I will astonish Paris with an apple" ("Avec une pomme, je veux étonner Paris"). 手元の書籍では Conversations with Cézanne, ed. by Michael Doran (University of California Press, 2001), p. 6 に、Gustave Geffroy, Claude Monet, His Life, His Time, His Works (1922) からの抜粋として記されている。結局驚いたのはパリに限られなかったけれども。
他の作品群
まっさらなキャンバスに描かれたのではなく、絵が描かれていたキャンバスの上から異なる絵を描いて完成している作品が多いようだ。後でギャラリストさんから伺った話によると、作家が、作品として成功とみなすことができるのは5枚制作してそのうち1枚程度とのことだった。成功しなかったキャンバスの上に新たに描くということだろう。
画家のサイトには
「何度見てもはじめて対峙したような。
そしてもう二度と見られないかもしれない。
そんな気持ちで日々絵描いています。」
と記されている。
今回の展示に際して書かれたArtist's Note
「制作は油彩画です。
静物画は自分にとって、じっくり(対峙でき)たゆまなく毎日描ける重要なテーマです。
アトリエに組まれたモチーフ(器や花や果物など)を、描いては消し、描いては消しの反復で生まれた、”思考の痕跡”のように思えるものも調子(濃淡)とした画肌になっていきます。
写真を模写しながらの制作ではなく、”今、目の前に見えているもの”を、そのまま自分なりの見方と考え方で捉えることを大切にしています。見慣れたモチーフも、初めて見たように、そしてもう二度と見れないかもしれないという気持ちで日々制作しています。
朽ちていく花や果実も、そのまま描きこんでいくため、描き始めたときのまだ瑞々しく、フレッシュな部分と時を経て朽ちた部分がひとつの画面に定着したような作品も多くあります。
“今、この目の前の事象”を表現できる方法であれば、モノクロームの単色画になったり、固有色からかけ離れた表現になることもあります
ときには、油彩にエッグテンペラやアクリル絵具を併用することもあります。」
と記されたあと、
「花や果物が確かに目の前にあった、(いまはもうない) 感が絵に出てくれたらと思って描いています。」
と結ばれている。
「確かにあった」と「いまはもうない」の、過去と現在の、生と死の間。間で消え去ったものは何だろうか。その消え去ったなにかと画家の間に絵画がある。その消え去ったなにかが、絵画とそれを観る自分の間にも絵画を通じてある種の照応関係を持って表現されている。そのように感じられてくる。そのような絵画を目指して描いているということだろうか。「いまはもうない」何かを描いているけれども画面は、画面から感じる印象は、静かだが非常に重い。いまはもう「ない」ものが、そのような静かな重みを持って確かに「在る」。特に購入した絵はそのように感じる作品だった。静かに祈るような心持ちで毎日観ることになりそう、と思った理由の一つはここにあるのかもしれない。
「静かないのち」。
「静物画」はフランス語ではnature motre「死せる自然」、英語では still life「(死んでいるから)動かない命」。「still」 には「静かな」「穏やかな」という意味もあるけれども、死産のことをstillbirthという。死んでいる・動かない・静かなのは、フランス語では自然、英語では命、日本語では物。
帰宅後、早速購入作品画像をラップトップのウォールペーパーとして設定してゆっくり観る。
YUKI-SISまでの移動中聴いていたのは Chicago Underground Quartet
.jpg)












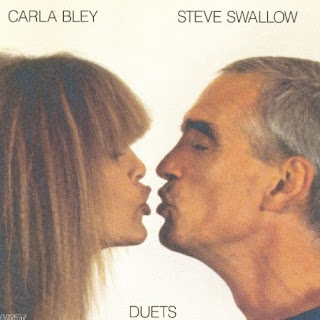


コメント
コメントを投稿