蝸牛あや作品を受け取り撮影し考える
(
某日。
エントリー「蝸牛あや展を観て作品を購入してウィスキーを飲む」で記したように、蝸牛あや作品を1つ購入していた。
購入時に店頭での受け取りをお願いしている。昨日、展示担当の方から受け取り準備ができている旨の連絡があった。
本日受け取りに外出する。交通機関を乗り継いで銀座駅で下車し銀座蔦屋に入る。
受け取る。
帰宅後の話。作品を扱う時用の白いコットンの手袋を装着して作品を取り出す。
撮影する。
タイトル: 音楽家/ Musician
制作年: 2023
サイズ: 333×333×55(mm)
素材: 絹糸刺繍、染め絹布、真鍮枠、木台
表図柄
裏
部分
エントリー「蝸牛あや個展を観る」で記したように、自分は2023年のメグミオギタギャラリーで開催された蝸牛あや個展「夜間飛行」で本作品を観て購入したいと思ったのだけれども購入する余裕がなく購入を見送ったのだった。
作品群はどれも良かったのだが、いくつかある作品モチーフの中で自分は葉のシリーズが特に好みだった。「夜間飛行」では葉のシリーズは5点展示されていただろうか。その中で、DMにも使用されていた、今回購入した作品に惹かれたのだった。楓あるいはプラタナスの落ち葉だろうか。なぜか今回の展示まで売れ残っていた。
枠としては、絹布をキャンバスのように矩形の枠にピンと張り刺繍したものよりも、購入作品のように絹布を真鍮の枠に糸で留め直方体の木の台に設置しているものに惹かれた。
まず、経年変化で錆びていくであろう真鍮が「落ち葉」の枯れ朽ちていく感じと響き合うこと。
次に、柔らかい絹布と絹糸が湿度で撓む、あるいは空気の流れで絹布が揺れる、そのことで刺繍部分も撓む。その撓みが現実の落ち葉の撓みを想起させること。矩形の枠にキャンバスのようにピンと張った布に刺繍が施されているのであれば、そのように撓まず平面のままだろう。
また、蝸牛さんの作品は見る角度によって刺繍糸の煌めきが変化する、あるいは変化するように制作されているのだが、そのように撓むことでも刺繍の煌めきが変化する。矩形の枠にピンと張った布に刺繍であれば布の撓みによる変化はあまりないだろう。
さらに、立体というよりは平面に近い葉っぱには表裏 (と人間都合でそう呼ぶとして) がある。葉の表裏にはそれぞれに機能があり、表と同様に裏も重要なのだろう。蝸牛作品モチーフの一つである貝は立体でありこの意味での表裏はない。あるいは別のモチーフである鳥の羽は葉っぱ同様平面に近いけれどもこの意味での表裏はなさそうだ。直方体の木の土台に支えられた真鍮枠に葉の刺繍が施されていれば、刺繍の裏面をいつでも見ることができるように設置できる。あるいはどちらの面が目に見える側でも設置の仕方は変わらない。直方体の木の台を前後180度回転させるだけでよく、180度回転させても形は同じ直方体のままだからだ。ある意味で表と裏は等価である。また、刺繍の表は刺繍をその形にする裏面がなければ成り立たない。裏は裏なりの機能と重要性がある。葉のように。そういうわけで裏面画像も掲載している。他方、矩形の枠にピンと張った布に刺繍をした場合、キャンバス同様、設置時に壁に枠を掛けるため裏面を見ることが難しい。裏面を見るならその度ごとに壁から外さないといけない。そして裏面が常に目に入るように設置するのは難しい。キャンバスの裏が表面になるよう設置するのが難しいように。表と裏に等価性がない。
というわけで、作品としての形態が葉のモチーフを引き立てるように感じられたのだった。
購入した作品には、作品と真鍮枠を覆い下の木の台にぴったりと合う厚さ6cmほどの薄いアクリルボックスが付いてくる。アクリルボックスを外して作品を設置しても、アクリルボックスを装着して作品を設置しても、どちらでも良い。上掲写真ではアクリルボックスを外してある。
今回の展示ではもう1点葉っぱ作品が展示されていた。
タイトル: 守り人 / Sentinel
制作年: 2024
サイズ: 118×155×5(mm)
イチョウの葉だろう。真鍮枠ではあるが木の台はない。壁設置になるだろうか。これの作品もタイトル込みで良いと思うけれども、購入した作品の方に遥かに惹かれたのだった。
真鍮枠作品は上記展示「夜間飛行」で初登場したようだ。上掲リンクのギャラリーによる同展説明文中に「今展では刺繍の新たな表現的挑戦として、生地の柔らかさ、弱さも魅力として見せることを意図し真鍮枠に張った作品」を展示します、とある。自分は「夜間飛行」でそもそも蝸牛作品を初めて観て知ったのだった。自分には良いタイミングだった。
今回購入した作品について、こちらに掲載されている作家の言葉では
「生地や糸は、石や金属、木、紙など様々な素材の中で、最も柔らかい素材です。
糸が生地の表裏を行き来して形を作りだす刺繍。その弱さや特性を見せる形に挑戦しました。
落ち葉のはらりとした様子が、生地の軽やかさと重なり、
見つけた時にタイトルが浮かんだものを作品にしました。
この作品には、バッハのインヴェンション第1番の楽譜が所々に縫われています。」
「落ち葉のはらりとした様子」と「生地の軽やかさ」の重なり。作品としての形態だけではなく、作品前の素材も葉っぱモチーフと響き合っている。
上記のようにタイトルは音楽家。銀座蔦屋アート担当の方を通じて、この作品の制作に関するコメントを作家さんから頂戴した。それによると
「葉っぱは、公園に落ちていたものを模写しており、葉脈が五線譜に見えたということから音楽につながります。バッハのインヴェンションという連弾曲があります。よく見ていただきますと、そのはじまりのあたりの音符が縫われおり、バッハの書癖まで模写して、刺繡を施しています。」
バッハのインヴェンション自筆譜のことだろう。そういうわけで上で部分画像3枚を掲載した。よく見ると音符の刺繍が施されているのがわかる。葉の模写に影響がない箇所あるいは葉の部分で音符に見えるような箇所に音符の刺繍がされているのだろう。
作家の制作についての考え。
作家のサイトから。
「手に針を持ち、糸を通し、その糸が在るべき場所に針を刺し、裏側を渡って表側に出すことを繰り返す。
糸はその瞬間の空気をふんわりと抱き、縫い留められていく。
昔々人々は戰の際、皮の盾に印や模様を縫い付けたという。私が刺繍を用いる理由のひとつは、消えてしまわないように確実に刻み付けたいからだ。
海や川で見つけた石や貝には、人と同じようにひとつひとつに長い物語がある。無数の凸凹、色や形、光と影を見る。糸を重ねる手法はぎこちなさを伴う。その時間の中で、果てしない想像を巡らせる。私の感情や意思から解放され、世界との接点を捉える。見つけたことを糸に封じ込めて永遠にする。
作業に深く集中している時は、深い海に潜って手探りで宝物を見つけようとしているような感覚になる。 その感覚をまた体験したい、完成を見たいと思い針を刺す。
どんなに時代が変わっても変わらないこと。それを捉えて、世界の誰か1人と響き合うことができたらいい。」
インタヴューにて。
「「確実に、痕跡をとどめて形にしたいという気持ちがあります。表面に乗せるだけじゃなくて、裏表通して縫い留めるということが、私にとっては大きな意味を持っていると思います」。そう出展作家の蝸牛さんは企画担当者のインタビューに応えている。表面に塗るのではなくて、そこに空気を含んだ糸を縫い留め置いていくこと――。そこが絵画との大きな違いだとも話す。」
裏面の重要性が示唆されていた。
メグミオギタギャラリーの上掲サイトより
「古来より刺繍は、家族をはじめとする共同体、あるいは個人に対する魔よけやお守りなど、「祈り」の象徴として受け継がれてきました。日本においては、飛鳥時代に聖徳太子の死を悼んで制作された「天寿国繍帳」(622年)が最古の遺品として知られています。洞窟壁画や装飾古墳に見られるように、描くことや装飾は自然と共に生きるために必要な祈りだったのです。しかし大量生産の時代に入り、純粋な祈りを形にするための手段としての刺繍は姿を変えました。蝸牛は、刺繍のはじまりである祈りの行為に立ち返り、願いを込めて作品を一針一針縫いとめることにより、現代にあるべきものを私たちに問いかけます。」
「「祈り」の手段として長い歴史をもつ刺繍に感銘を受け、様々な地域の技法を学ぶ。現代において形式化した祈りを、一針一針思いを込めた作品を通してその本質へ導く。」
「祈り」。エントリー「ただあやの個展を観て作品を購入し料理を作る」で記したように、最近、大掛かりな施設での祈りではなく、毎日の生活での祈りのような気持ちを受け止める感じのする作品に惹かれることが以前よりも多くなっている気がしている。蝸牛作品もその流れのようだ。そうでない作品で惹かれる作品があることは変わっていないけれども。
Ketil Bjornstad and David Darling, Epigraphs
を聴きながら撮影し観る。この音楽も自分の中では「祈り」に通じている。
自分にとって素晴らしい作品をお迎えすることができてとても嬉しい。
6:00 起床。
グラス一杯の水を飲んで柱サボテンとボトルツリーをヴェランダに出す。
シャワー。
大きめのカップに珈琲を淹れる。オーガニック豆 20g、260ml。飲みながら読書。
9:00-9:30 第一食。自炊。マグネシウム (にがり顆粒 2g)、ビタミンB (Dear-Natura Mix)、ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g)、ビタミンD3 (Health Thru Nutrition 10,000Iu)、亜鉛 (Dear-Natura, 14mg)、ルテイン、ゼアキサンチン、コリンサプリ、タウリンサプリ (1000mg)、ナイアシンアミド (500mg)、イヌリン粉末 6g、グリシン粉末 3gを摂取。
ストレッチ。ホットココア (オーガニック、非アルカリ処理)。
音楽、雑用、休憩、読書。
15:30-16:00 第二食。自炊。ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g程度) を摂取。
オーガニック生姜粉末を溶いた熱い生姜湯を飲む。
外出
)








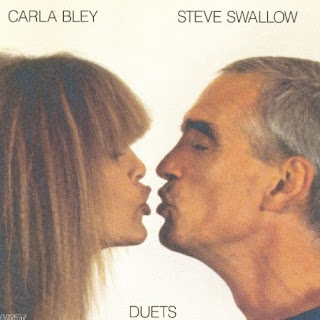


コメント
コメントを投稿