絵画の色彩に関する書籍を読了し所蔵するqpさんの作品を改めて観る
(
某日。
終日在宅。
などをかける。
Marcia B. Hall, The Power of Color: Five Centuries of European Painting (Yale University Press, 2019)
を読了する。個人的な好みとして、総じて18世紀の絵画は他の世紀に比して面白さに欠ける。書籍がカヴァーするのは15世紀から19世紀までの500年。20世紀以降の絵画の流れへとして同世紀初頭のマティス、ピカソ、カンディンスキーを論じるところで終わっている。
何年後かに再読しそうな予感を抱かせる良書だった。
この書籍に触発されて自宅にある色彩を改めて観ている。エントリー「ヨーロッパ絵画における色彩に関する書籍を読み、自然草木藍染糸の色彩を堪能する」「桂離宮についての書籍を買い逃し、所蔵する小林達也さん・内海聖史さんの絵画を観る」「所蔵する矢野静明さんの赤い作品を観て料理を作る」「所蔵する矢野静明さんの青い作品を改めて観る」の流れ。
自分が所蔵するqpさんの3作品を観る。
全て水彩の色。サイズは大きくても170x122(mm)ほど。筆ではなくスポイトなどを使用して水滴の水彩によって描いている。
優しい色彩・図形の配置・小さなサイズということで、観ると一瞬心が和む気がする。観ていると、しかし、各水滴のサイズ・紙の傾きによるその形態の変形可能性・湿度による乾き具合の違いで生じるであろう制御の難しい微妙な色彩のむら、が画面にもたらす静かな持続する緊張感が漲っているように感じられてくる。和んでいる場合ではなくなる。
色彩の良さは共通している。また、自分はWolsやパウル・クレーの小さなサイズの水彩作品も好んで見ているから、そもそも好みの作品系列なのだろう。
1枚目の作品は、完成しているがすぐにも未完成に解けて行きそうなところを堪えている。あるいは手を加えれば全く別の完成態が実現する、そういう動的な実現可能性をいくつも孕んでいる。そのように自分には感じられる緊張感に惹かれる。
2枚目の作品は、自分が高密度な画面を好む傾向があるのに加えて、もうこれ以上手を加えることができない静かな緊張感のある完成態だと感じられる。
2作品の間にはこうした緊張感の対比がある一方で、色彩の流れとしては左側のオレンジ・黄色系からブルー・紫系に移行していくという共通点がある。
2枚目の作品を1枚目と合わせると、対比と共通点から、1+1が2以上になるようなペアになると、直感的に判断したのだろう。
3枚目の作品は先の2作品といくつかの点で異なっている。丸い図形が目立つこと。図形の大きさのばらつきが大きいこと。他の2枚は奥行きを感じない構成になっているのに対して色彩の明度と彩度によってある種の奥行きがあること。関連して、視線が中心を持たず拡散するというよりは、一度中央に向けて集中させるような構図になっていること。など。
色彩の良さは共通している。3枚で良い組み合わせになったと思う。
色彩を堪能する。
上記のことは、エントリー「花を巡る1日: 高田馬場でqp個展を観て作品を購入する」「qp個展で購入した作品が届く」「青木陵子・qp・工藤麻紀子3人展を観てqp作品を購入する」「購入していたqp 作品が届く」でも記している。
6:00 起床。NY市場終値をチェック。
グラス一杯の水を飲んで柱サボテンとボトルツリーをヴェランダに出す。
シャワー。
大きめのカップに珈琲を淹れる。オーガニック豆 20g、260ml。飲みながら読書など。
スロージョギング。腕立て伏せ10回x 10セット。
9:00-9:30 第一食。自炊。マグネシウム (にがり顆粒 2g)、ビタミンB (Dear-Natura Mix)、ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g)、ビタミンD3 (Health Thru Nutrition 10,000Iu)、亜鉛 (Dear-Natura, 14mg)、ルテイン、ゼアキサンチン、コリンサプリ、タウリンサプリ (1000mg)、ナイアシンアミド (500mg)、イヌリン粉末 6g、グリシン粉末 3gを摂取。
ストレッチ。ホットココア (オーガニック、非アルカリ処理)。
音楽、雑用、youtube.
15:30-16:00 第二食。自炊。ビタミンC (L-アスコルビン酸 1.5g程度) を摂取。
休憩。雑用、音楽、読書。
マグネシウム (にがり顆粒 2g) を摂取。
Coconut oil pulling、軽くストレッチと腹式呼吸、就寝。
)


11:17.jpg)
3:7.jpg)
3:15.jpg)
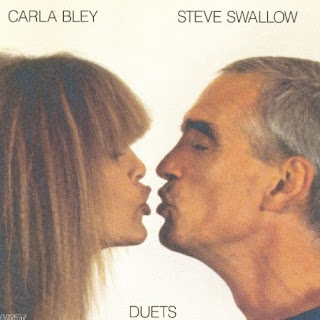


コメント
コメントを投稿